ベビーフードで有名な和光堂が、昭和30〜40年代に展開した自社ブランド。実際の製造販売は子会社・関連会社の複数工場が担った。
具体的には紆余曲折を経て同一グループとなった三和乳業、長水農工利連(ノーコー牛乳)、北部酪農協の3者だが、本項では、昭和34年に三協乳業(サンキョー牛乳)と業務提携し、「北酪牛乳」改め「和光牛乳」に転じた、北部酪農協から変遷を辿る。
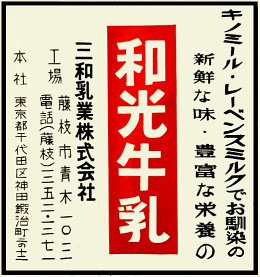 | |
【付記】 三和乳業と長水農工利連の和光牛乳
三和乳業は和光堂傘下の練乳・粉乳メーカー。34年、藤枝工場(静岡県)の操業を開始。同年、北部酪農協および長水農工利連がサンキョーと提携。各社とも和光牛乳の生産に着手。
つまり和光牛乳は、少なくとも系列下3工場で作られ、それぞれの商圏に流通した。発売の後先は不詳。販売量から見て、北酪が生産のメインではあったらしい。掲載瓶は工場違いの2種と見られる。
画像左:和光牛乳(三和乳業)の広告(昭和34年) |
|
◆南信酪農協・森永からの離脱
県南一帯は森永乳業が乳牛の普及奨励を行い、集乳基盤を形成したところ。昭和23年に発足の南信酪農業協同組合も、原料乳出荷をメインに運営されていた。
南酪さん自ら市乳事業を行う意欲もあったが、森永が困るというので渋々納得のところ、25年、同社は買取乳価の大幅値下げを通告。交渉は実らず、承服しかねた一部の酪農家は、南酪の副組合長・桑沢浜氏を中核に、別途、北部酪農組合を興した。
◆北酪牛乳の始まり
北酪グループは森永への送乳を中止。当初は山梨県酪連、26年には諏訪産業・伊那工場(⇒保証牛乳グループ)を出荷先とし、南酪より完全に離脱。28年、北部酪農業協同組合の設立認可を受け、翌年に念願の独自ブランド「北酪牛乳」の製販に着手する。
まずは上伊那酪農組合のミルクプラントに処理を委託。間もなく自工場を辰野町の事務所に併設して一貫体制を整えた。この頃の売上は一日わずか90本、苦しいスタートだ。
◆諏訪産業の頓挫・サンキョー登場
北酪牛乳の市場展開ままならぬ昭和30年3月末、主要な原乳卸し先・諏訪産業が経営破綻、事業を停止。俄かに厳しい局面を迎える。※同様に諏訪産業へ生乳出荷していた長野市の長水農工利連も事態に窮し、その後、和光堂・三協乳業と結び付く。
この際、県の畜産関係団体の支援に加え、三和乳業(和光堂)と武田食糧(武田牛乳)、そして諏訪産業も出資参画した三協乳業(株)が新しく出来、伊那工場の存続が成って危機は解消。やがて北酪牛乳も何とか日量3千本まで伸びてゆく。
◆三協乳業と提携・和光牛乳へ転換
市場競争の激化に鑑み、昭和34年、北酪は三協乳業と業務提携。組合は生産処理、サンキョーが販売を担う分業に移行。結果「北酪」銘は終売。新たに「和光牛乳」の売り出しへ。
三協設立に携わった三和乳業は、和光堂の子会社。北酪の市乳を大株主のラインナップに組み込む形。掲載瓶の広告欄は育児粉乳・レーベンスミルク(⇒同銘の現行商品)。そもそもサンキョーの発起は粉ミルクの増産が主目的で、和光堂の関与が大きかった。
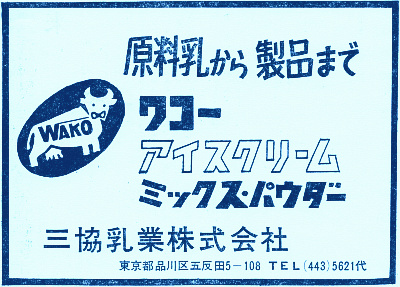 |
|
画像上:三協乳業(ワコーブランド)の広告(昭和40年)…三和乳業は昭和36年にサンキョー牛乳へ合併し、同社が製造を引き継いだ。ブランド受託の経過は少しややこしい。 |
◆伸長と終焉・その後の北酪
北酪製造の和光牛乳は好調に推移。昭和36年で日量1万3千本、同40年は日量3万本。学校給食は18校に納入、年間累計100万本に達した。しかし昭和49年頃、北部酪農協の工場は閉鎖、「和光」銘も同時期に廃止へ至る。
三協乳業は当時、サンキョー/武田牛乳ほか、複数のブランドを取り扱い。49年は静岡県乳業(ケンニュー)の工場継承もあり、拠点集約・合理化を図ったのではと思う。
北酪は市乳処理より撤退後、生乳生産に専念。主に三協の伊那工場?へ出荷も、平成12年に同社は解散。前後して上伊那の酪農4団体は集送乳の統合に踏み切っている。