戦前〜戦後の約10年間に渡って商われた農系ブランド。東京近郊の地の利を生かし、特に昭和20年代の最盛期は明治・森永の大資本へ肉薄する規模を誇ったが、間もなく経営不振に陥り協同乳業(名糖牛乳)へ事業譲渡。昭和32年、銘柄は消滅した。
景品コップにその姿を留める往時のゆるキャラ、アイキャッチの「たまちゃん」。いったい何をモチーフにしたやら想像が難しい。クローバーと赤ちゃん(哺乳瓶)の合体だろうか。
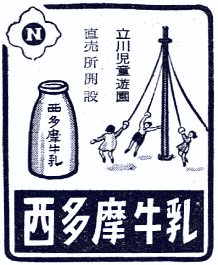  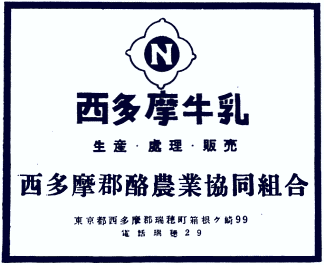 |
|
画像上:西多摩牛乳の新聞広告(昭和28年)と、西多摩郡酪農協の団体広告(昭和30年)…「立川児童遊園 直売所開設」今はあまり見掛けなくなった遊具・回旋塔のイラストが載っている。戦後盛業の時代。生産・処理・販売の一貫体制をアピール。福生新聞(福生デジタル)および[農林省年報1954]より。 |
◆瑞穂町酪農の萌芽・奥多摩酪農組合
町域の農業は畑作・養蚕が中心、家畜導入は全般的に低調だった。明治中期〜大正期に、東京市部や狭山の業者の求めに応じて仔牛の育成が始まると、地元に3〜4軒の牛乳屋さんも現れ、各々数頭ばかり乳牛を繋いでいたという。
育成受託は農家に現金収入をもたらすが、利の薄い悪質な仲介も多い。そこで昭和9年、ウシに将来を見た川合藤吉氏ら有志11名が参集、奥多摩酪農組合を結成。組合は練馬の阪川牧場と特約を結び、仕事に専念できる環境を整えた。
◆市乳事業へ進出・戦時の窮乏
酪農が盛んだった伊豆大島出身者の指導を得て、徐々に管理技術が向上。組合は生産・直売を志向する。昭和16年、郡全域を集乳エリアに定め、西多摩牛乳販売購買組合として自ら処理工場を建設、ついに市乳事業へ乗り出した。
生産・処理・販売の一貫体制を構築も束の間、戦争が始まって物資は払底。19年に企業統制令で東京牛乳乳製品統制(株)(のち東京乳業)への併合を余儀なくされる。敗戦復興の混乱期にも落伍者が続出、牛飼い激減し苦しい局面を迎えた。
◆農協の設立・西多摩牛乳の快進撃
しかし昭和23年、農協法のもと西多摩郡酪農業協同組合が成り、戦時に東京乳業へ現物出資を強いられた町の処理工場を取り戻すと、他社に先駆けて事業を再開。大消費地に近く、飲用需要は激増。西多摩牛乳は急速に復調・拡大した。
昭和27年、南多摩・西多摩・北多摩の3組合は、三多摩酪農協同組合連合会を結成。三鷹市に共同工場を設けるが、稼働の9割は西多摩案件。同29年には西多摩が完全吸収し、2工場体制を確立。傘下販売店は100に迫る勢いだった。
原料乳集荷は多摩地区に加え、隣接する埼玉県入間・比企郡一帯に及び、西多摩ブランドは東京市乳界で明治、森永、保証に次ぐ4大メーカーと言わしめる大成長を実現。当時の農民経営では破格の規模であり、目覚ましい成功例と評された。
◆協同乳業(名糖)の買収・直販撤退
好調は数年のうちに行き詰まる。市場競争の激化、景気後退に供給過剰、売掛金の回収不良、乳代支払遅延や設備投資の困難に直面。折りしも首都圏進出を期した協同乳業に呼応し、昭和31年、瑞穂町と三鷹市の2工場及び営業権を譲渡する。
その後も約一年間、協乳傘下で「西多摩牛乳」銘を続投も、市乳製品が「名糖」ブランドへ統一された昭和32年に廃止。掲載瓶は末期流通・最終世代と見込まれる。
◆名糖時代の流転・変遷
協同乳業は買収拠点を東京市乳第1工場(三鷹工場)、同・第2工場(瑞穂工場)と位置付けたが、いずれも短命に終わる。敷地狭隘な三鷹工場は大型乳機の導入不可、「経営上大きなマイナス」で昭和41年に閉鎖。労使紛糾し裁判沙汰になった。
瑞穂工場は昭和33年、消費拡大・集団飲用促進のため10円牛乳に参入。協乳が便宜的に設立した東京牛乳(株)のミルクプラントへ転換。新たに「東京牛乳」を売り出す。
しかし景気好転につれ諸物価は上昇。売値10円の維持が困難になると、36年に生産を中止。東京牛乳は解散、同時に瑞穂工場も閉鎖されている。わずか3年の短い商売だった。
◆半世紀を経て「東京牛乳」が復活
瑞穂工場の所在には組合の拠点が残り、今なお東京都酪農業協同組合(平成8年に合併誕生、旧・西多摩酪農協を包含)が事務所を構える。さらに時は流れて平成18年、農協は地産地消の新ブランド、その名も「東京牛乳」を旗揚げした。
共同開発・製造担当は協同乳業・東京工場(多摩酪農家発東京牛乳)。過去の経緯とは無縁の新規事業で、復刻商品のポジションにはないが、歴史的には半世紀の雌伏を経て「東京牛乳」堂々の再デビュー、と言えるかも知れない。
― 関連情報 ―
西多摩牛乳のノベルティーコップ
(牛乳グラス☆コレクション)
協同乳業の紙パック製品
(愛しの牛乳パック)
協同乳業・三鷹工場の紙栓
(牛乳キャップ収集家の活動ブログ)