明治23年、神戸駅前の小さな牛乳屋さんに始まり、戦後は小野市に牧場・工場を新設。今や継承5代・125年の歴史を刻む老舗メーカー。
昭和25年、(株)共進舎牧農園として法人化。平成に至って製販部門を分割し、(株)共進牧場を別途設立している。かつて一帯には伊坂牧農園、森本牧農園、あみ義牧農園など、複数の「牧農園」が営業。搾乳業者の典型的な名乗りだったらしい。
 |
|
画像上:共進ミネビタ牛乳の広告(昭和35年)…掲載(2)番該当のアイテム。 |
◆港町に牛乳屋さんを開く
創始は中尾うた氏、ご婦人の起業による。貿易で賑わう街のこと、欧米文化の流入も顕著で、日本の食生活の貧弱な側面が露わとなる。両親の実家が牧場をやっていたこともあり、中尾氏は滋養豊富な牛乳を市民に供給しよう、と思い立った。
・2019年度酪農乳業産業史シンポジウム
(Jミルク)
ただ、確認できる各種資料の古い記録では、大正12年から戦前期まで「共進舎・深川隈太郎」さんのお名前が上がっており、この頃は店の切り盛りを別の人?に任せていたようだ。戦後の代表は、再び中尾姓の方に戻る。続柄は良く分からない。
◆郊外移転と生産規模の拡大
転機は昭和22年、創業者の出生地・小野市青野原に共進牧場および飼料畑を拓いたこと。たぶん敗戦の混乱と物資欠乏で原料乳を充分に確保できず、自家搾乳の拡大をもって難局を乗り越えようと、奮発したのだと思う。
処理・販売の拠点は引き続き神戸市街に置き、自営牧場から鉄道と荷車で日々の生乳を輸送。昭和31年に牧場は小野市浄谷町へ移転、間もなく同地にミルクプラントを併設して現体制が確立。本社機能と生産部門の役割分担が成った。
◆ミャンマー支援と作蔵梅酒、馬乳酒の展開
前会長の中尾作蔵氏はミャンマー支援の諸活動で知られる。氏はビルマ戦線(インパール作戦)に従軍、悲惨な敗走を経て捕虜の身となり、計5年を過ごす。現地の人に助けられた恩に報いるべく後年再訪、練乳製造や梅の植林ほか、事業普及を手掛けた。
・ミャンマー皆好会のあゆみ
(NPO神戸ミャンマー皆好会)
・ブランド名を「作蔵梅干」「作蔵梅酒」と命名
(ミャンマー好きなヒト集合)
・メイミョー産青梅の作蔵梅干と作蔵梅酒販売を開始
(PING LONG)
昭和50〜60年代には共進舎と井上乳業(井上牛乳)が協業、東南アジアに広く親しまれる馬乳酒・乳酸飲料(クミス)を牛乳で作る技術を得て、販売会社「クムイスジャパン関西」を発足。しかしこの味覚を日本に定着させるのは難しかったようだ。
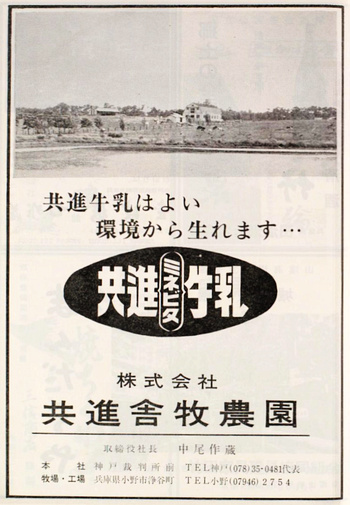 |
|
画像上:共進ミネビタ牛乳の広告(昭和42年)…中尾作蔵氏のお名前が見える。 |
◆掲載瓶と近年の印刷ビンについて
掲載は往年の「共進ミネ・ビタ牛乳」(加工乳)専用瓶装。公式サイトでは昭和50〜60年代のテレビCM(共進牛乳のうた)を公開中。古い瓶詰めラインもちょっと映っている。
印刷瓶の最終世代は900cc大瓶にトレードマークの仔牛を、一合瓶には昔の牛舎とサイロのイラストをあしらった姿。後者は観光牧場(共進ファミリー牧場)の一角、ご当地レストランに改装された所だ。(⇒番外編・共進牧場ミルカーズ/むにゅ’s
のぉと)
牧草を貯留する屋根付きサイロは昭和20〜30年代、神戸市域の酪農家が競って設置した象徴的な施設。どこにでもありそうなイメージだが、北海道以外だと実は珍しいという。
◆現行ビン製品の委託先について
平成23年に自社の瓶詰めラインを大幅に削減、学校給食向けビン牛乳も廃止。過去の定番・茶刷り200cc瓶(⇒ぽんげ乳業・兵庫県/北摂百貨天)は終息して久しい。
ビン製品は安来乳業へ委託、プラ栓+シュリンク包装に移行。大瓶だけは自家処理・紙栓仕様を継続も、丹波乳業の請け負いを経て平成27年頃、同じく安来乳業のOEMに変わった。
ところが平成31年、安来乳業は経営難で廃業。同社は島根県・安来市酪農農協と、大阪市住之江区の(株)いかるが牛乳の共同出資会社であったため、以降いかるが請け負いとなり、現在は無地の菊型飾り瓶(180cc)、牛乳・コーヒー・フルーツの3種のみが残る。
― 参考情報 ―
ビン牛乳 尼崎で健在 兵庫県内唯一 (神戸新聞NEXT)
共進牧場見学 in
兵庫県小野市 (杉本建設株式会社)
共進舎牧農園の紙栓(1)
(2) (3) (4)
(牛乳キャップ収集家の活動ブログ)
同・紙パック製品
(愛しの牛乳パック) / 兵庫の牛乳キャップ (職人と達人)
共進牧場 ミルカーズ (Aちゃんの湯遊自的生活)